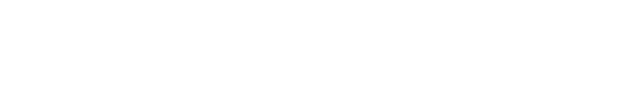粉瘤の切開排膿とは?治療期間や完治までの流れをわかりやすく解説
粉瘤は皮膚にできる良性の腫瘍で、多くの場合は命に関わるものではありません。
しかし、炎症や感染を起こすと強い痛みや腫れを伴い、「切開排膿」と呼ばれる処置が必要になることがあります。
「切開排膿」と聞くと、どのような治療なのか、どれくらいで治るのかと不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、切開排膿の内容や治療にかかる期間について、わかりやすく解説します。
形成外科と美容外科のクリニック池袋では、患者様一人ひとりの症状に合わせた粉瘤治療を行っています。
粉瘤の治療をご検討中の方は、ぜひ当院までご相談ください。
粉瘤の治療期間はどのくらい?粉瘤の症状別の目安
粉瘤の治療期間は、炎症の強さや膿の量によって大きく異なります。
また、切開排膿は応急処置であり、根治には袋の摘出手術が必要です。
炎症の程度による治療期間の目安は次の通りです。
炎症が軽度の場合
炎症が軽度の粉瘤では、切開して膿を出したうえで、そのまま袋を一緒に摘出できることもあります。
このケースでは再手術が不要となり、1〜2週間程度で傷が治癒することが多いです。
炎症が強い場合
炎症が強いケースでは、治療が長期化し、完治まで数か月かかることがあります。
炎症や腫れが強い場合は、まず切開して膿を外に出し、炎症を鎮めることが優先されます。
この段階では袋を完全に取り除けないため、いったん膿を排出する応急処置を行い、炎症が落ち着いてから再手術を行います。
再手術までの期間は通常1ヶ月程度が目安で、根治にはこの再手術が欠かせません。
切開排膿の治療の流れ
粉瘤が炎症を起こしている場合、治療は「切開排膿」という処置から始まります。
ここでは、実際の治療の流れを順を追ってご説明します。
診察と検査
医師が患部を診察し、粉瘤の大きさや炎症の有無、膿の量を確認します。
必要に応じて、超音波検査で内部の状態を詳しく調べることもあります。
局所麻酔
切開前に局所麻酔を注射し、痛みを軽減します。
麻酔がしっかり効いてから行うため、処置中に痛みを感じることはほとんどありません。
切開排膿
麻酔後、粉瘤を小さく切開し、膿を排出します。
軽度の炎症であれば、この段階で袋ごと摘出できる場合もあります。
粉瘤の袋の摘出手術
炎症が強く、初回の処置で袋を取り除けなかった場合は、炎症が完全に治まってから改めて袋の摘出手術を行います。
手術後は傷の状態や腫れの程度にもよりますが、通常は数日~1週間程度で傷口が治癒するケースが多いです。
粉瘤で切開排膿が必要になるのはどんなとき?
切開排膿が必要になるのは、粉瘤が細菌感染を起こして炎症が進み、内部に膿がたまった「炎症性粉瘤」の場合です。
通常の粉瘤は痛みがありませんが、炎症が起きると赤く腫れ、熱を持ち、強い痛みを伴うのが特徴です。
放置すると日常生活に支障をきたすこともあるため、炎症性粉瘤が疑われる場合は、早めに受診して治療を受けましょう。
粉瘤治療は形成外科と美容外科のクリニック池袋へ
当院では、粉瘤の大きさや状態に応じて適切な方法で治療を行っています。
小さな切開で袋ごと粉瘤を取り除く「くりぬき法」を中心に、必要に応じて切開法での対応も可能です。
形成外科専門医である院長が診療を担当するため、再発リスクを抑えつつ、傷跡や仕上がりにも配慮した治療を受けていただけます。
粉瘤治療について不安をお持ちの方は、どうぞお気軽に当院にご相談ください。